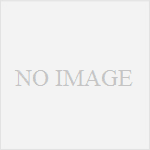今は絶賛プライドマンスの期間ではあり、去年のこの期間より明らかにわたしの意識は異なっている。なんというか、自分の中にもう一人、正確には自分がずっと昔から知っていて、だけど知らないふりをしている自分の存在を強く感じるようになった。それはおそらく、去年ごろからもう取り繕ったり、何とか適合するために、といった生き方を辞めて自分のなりたいような表現を心がけるようになったことと関係している。その辺の話は前の記事でも話した通り。そして、それを知るための手掛かりとなりそうな一冊が、「ノンバイナリー 30人が語るジェンダーとアイデンティティ」だった。そしてそれをようやく読み終えた。
感想としては、一言でいうならば、自分の存在が許されたような、そんな気分になった。それと同時に、自分の存在というのはどこに位置するのか、ということを今すぐにはっきりと言語化することは難しいだろうし、多分しなくてもいいのだと思えるようになった。だけどしようとする試みを辞める気はない、多分それは生涯かけての長い旅をすることで、ようやくできる事なんだということを、本書で寄稿されていた30人のノンバイナリーたちの旅の記録からも感じ取れた。
本書に寄稿された30人のノンバイナリーは、年代も、国籍も、職業もまちまちであり、特定の領域に偏って選ばれているわけではない。10代もいれば50代だっている。西欧の白人だけでなく、中国系やアフリカ系の人もいる。学者だけではなくパートナーと子供を持った人もいる。いわゆる「ステレオタイプ」を形成するような人選や表現にならないような構成となっていた。
そしてそれが、わたしが知らず知らずのうちに形成していた「ステレオタイプ」な、もっと言えば「理想的な」「ノンバイナリー」を内包していたことにも気づかされた。そしてそれが、自分の存在の一について考えるうえで大きな障壁となっていたことにも。
わたしは、ノンバイナリーというのも、トランスジェンダーを始めとしたジェンダークィアも、幼いころからずっと出生時に割り当てられた性に違和感を持ち、それが大なり小なり幼少期からの価値観形成やコミュニティでも影響があるものだと思っていたのだ。だから、そういうのがない自分には当てはまらない、いや当てはめること自体がクィアの概念の収奪になるかもしれないという恐怖があった。
そんな自分の思い込みを、本書の寄稿者たちは自らの旅の記録をもってして丁寧に崩してくれた。寄稿者の中にも、自身の体験が現在のクィアコミュニティの中でそのアンブレラ(傘下)に入るほどのものなのか、ということに悩んでいた人がいて、それでも向き合い続けて、理解ある人に出会えた結果、考えを進めることができた、という。更には、そういったわたしの思い込みのようなジェンダークィアの「ストーリー」が、どの程度ならばクィアと言える、などといった枠組みを設けるのは、違和を感じながらもそれとは違うと、それには及ばないと思ってしまった人を排除する方向に働く、悪しきエリート主義だと断ずる寄稿者もいた。そこで依然読んだ「バトラー入門」が刺さる。既存のストーリーに当てはまらないならば、自らの居場所を、自らのアンブレラタームを作り出してしまえばいい、というものが。そもそもジェンダークィア自体が一本線のジェンダーバイナリー上にあるものだけではなく、現在はインターセックスという視点を持たなければ見落としてしまう存在が多すぎる。だから、それらの寄稿者の旅路が、「そんなことで自分は違うかもしれない、などと縮こまらなくてもいい」と言ってくれているような気がした。だけど、どの寄稿者に共通して言えるのは、考え続けることを決して辞めていなかったことだ。だから、縮こまらなくてもいいけど、考えることを辞めてもいけないとも思えた。縮こまって考えを止めてしまうのが一番悲しいことなのではないだろうか、とも。
また、自分を取り巻くジェンダーロールに対しての違和や不快感を感じるのが、大人になってから、という寄稿者もいた。その理由は、子供のころに適切な教育を受けられずに、そもそもそのロール自体がおかしかったことに気づかなかったこと、自分を表す適切な概念を知らなかったこともあれば、両親、友人、周囲、環境に適合するために子供のころにあえてその違和を捨てることで、環境の思うがままの自分でいた人もいた。これもわたしに大きく刺さった。わたしは、ジェンダー・アイデンティティに関する知識をまともに得られたのは、2010年代後半になってからようやくだった。それまでずっと知らずに、そして、自分のふるまい次第で周囲が一気に敵意を向けてくることに恐怖を抱いた子供時代に、それらの感性や振る舞いを全部捨ててしまったから。しかし自分が適合しないジェンダーロールに、ジェンダー規範に無理に乗ろうとしても結局乗り切れずに、子供のころの自分は常に「いじられ役」か「透明人間」といった、軽んじられる存在でしかなかった。今思えば当然だろう。端的に言えば「人の顔色をうかがう人間」でしかなかったんだから。
知ったからにはもう戻れない。これは今年見た映画ウィキッドでも主人公エルファバが終盤に口にした言葉だが、今の自分にもよくあてはまる。もう過去の何も知らずに無理に規範にはまっていたころには戻れない。その先に幸せは待っていないんだから。寄稿者たちも、規範に無理にはまっていたり、流されていた状況を自ら動かすことで、自分を生きている。そしてそうあることを、自らの旅路をもって、同じように違和を、苦痛を、悩みを抱えている人たちに「許し」ている。わたしは10代のころには性的違和を抱えていなかった、正確には自分の今迄に合った思いに性的違和があったとしてもそれに気づかなかった。ずっと自分の出生時に与えられた性に求められる役割を数年前までずっと果たそうと不適合ながらもがいていた。それは周囲の顔色を窺っていて生き生きともしていないから魅力的な人間にも映らなかった。しかし、そんな人間が今になってやっと抱える、そして振り返る性的違和を、そしてその先自らが最も自分で在れる在り方を選ぶことを「許し」てくれている。そう思わせてくれる一冊だった。
そしてそれらとは一風変わった視点で、そもそも社会がジェンダーバイナリー上の両極のどちらかの者、とされているあらゆるものも、別にそれらのものじゃない。自分が自分のものかそうでないかを選ぶことができ、それらから自分というジェンダーを作っていくんだ、という寄稿者もいた。その考え、アリ!と思ってしまった。わたしも大概に欲張りだから。そして自分の全部を捨てたいわけじゃないんだってことを、そう思うことで改めて実感もした。
その結果、わたしのジェンダー・アイデンティティへの思考はかなり進んだ気がする。この一冊は、きっと自分のジェンダーの旅路に迷いや躊躇が生じた時に、また読むことになるはずだ。「アルジャーノンに花束を」に続き、このように自分の旅路につまずいたときの支えになりそうな本に連続してであるのは本当に幸福だ。この出会いに感謝したい。