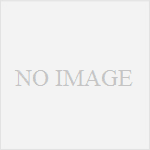私は、読書家と言えるほどたくさんの本を読んでるわけではありませんが、読書が好きです。基本的にヘイト本でない限りジャンルは問わず。
その中でも、自分の思考、知性を磨ける、著者の信念が丹念に描かれた、事実をもとにしたドキュメンタリー系や、社会秩序からはずっと透明化されていたけど、確実にずっと存在していた者(人、動物問わず)たちを描くクィア文学が好きです。
そして、最近はシスターフッド、というジャンルに惹かれています。シスターフッドというのは、人文書院「布団の中から蜂起せよ アナーカ・フェミニズムのための断章(高島鈴:著)」によると、1960年ごろに生まれた言葉で、ラディカル・フェミニズム※1の文脈で掲げられてきた概念だそうです。生活の隅々にまで男性支配が染み渡っている圧倒的男性優位社会である現代(というか昔も?)においては、フィクション上も社会上も女性は男性との関係上でしか語られず、男性に従属する、あるいは常に男性の目線で語られることが多く、女性同士の関係というのが軽視されており、ひどいときは分断をあおるような切り口で語られることも少なくはありません。具体的には「女の敵は女」とか「女同士の関係はドロドロしている。それに比べて男同士や男女の恋愛は~」とか「女の友情は脆い」とか正直かくことすら苦痛なのですが、少なくない回数耳にしたことや目にしたことはあると思います。
シスターフッドというのは、そういった男性優位社会による女性が男性ありきで語られる抑圧の実態や女性同士の関係の分断に対する抵抗、つまるところの抜本的な、根本的な変革を描いた文学、ということになります。だから、登場人物は、常日頃仲がいいとも限らないし、趣味嗜好が共通しているとも限らない。でも、抑圧や文壇、搾取などといったものに対しての抵抗、その一点においては考えを同じくする、つまりは連帯できる。そういった関係性のものが多いです。
そのため、このジャンルにおいては家父長制を筆頭とした抑圧装置の存在は避けては通れないものとなっております。それらによる抑圧は当然描かれるし、それに対してどのような形で抵抗し、関係が築かれていくか、といったものが全体的な特徴と、考えられます。
※1 「根本的な」「抜本的な」といった意味でのラディカル。インターネット上ではよくラディカルは「過激」といった意味で用いられることが多いので念のため。
シスターフッドにはまったきっかけ
このジャンルにはまる前は、そういった女性同士のつながりや関係を主軸に置いた作品については、自分自身、文学にしろ映像作品にしろ現実に還元する、現実に帰るためのものと捉えているため、家父長制などの抑圧装置に無自覚だったりその存在を知りながら受容するタイプのものについては、どうしてもシスジェンダーでヘテロセクシャルの男性の目線を感じてしまい(要するにシスヘテロ男に都合のいいタイプの作品だと感じてしまう)、どうしても現実から逃げる、もしくは現状追認のように見えてしまっていて、シスターフッドという概念にまでなかなかたどり着けずにいました。
本格的にこの概念を知ろうというきっかけになったのは、2023年の下半期に触れた書籍「ピエタとトランジ(著:藤野可織)」と、映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」の二つでした。この2作品をほぼ同時期に観賞したことは、自分にとって大きな変革をもたらしたと言っても過言ではなかったです。どっちか単独だと、多分この変革は起こらず、シスターフッドという概念を知るのはもう少し先になったと思います。
「ピエタとトランジ」は、自身の周りで殺人事件が起こる体質(伝染性あり)を持った天才的な頭脳を持った女性トランジと、語り手でもあり彼女の非日常性に興味を持った、トランジの体質が全く伝染しないピエタの、高校生時代の出会いから終焉を迎える老年期迄を描いた小説で、彼女らが彼女らとして存在し続けるがために、世界の方が滅んでしまうという、「我が道を行く」を何があっても貫き通す二人の姿と、あるシーンと重なるラストシーンに爽快な読後感を得られる作品でした。彼女らに立ちはだかる障壁は、『子を産み育てて家庭に入るということを至上の幸せとし、社会秩序上は何も担保されない関係であり続ける二人の在り方を批判し、遂にはトランジの体質が移って一時期二人を引き裂くきっかけになる大学時代からの友人』、『トランジ不在の放心時にピエタと関係を持ち、遂には彼女の意向を無視し子供を持つことを迫ってくる社会的な立場も保証されたピエタの夫』、『トランジの体質から彼女を悪魔視し、捕えて検証しようとする国家機関とピエタには善良で男に尽くす女性像を求め関係を迫る男エージェント』、『ピエタとトランジの関係が世界をめちゃくちゃにしたと原因付け、当に老人となった彼女らを始末しようとする家父長制復権を掲げる団体』といった、すべて男性優位社会、家父長制の抑圧装置と関連する、ファンタジーではあるけどリアリティも担保されており、その中で死ぬまで変わらない関係性と自己を貫く二人の痛快さをより引き立ててたと思いました。
んで、そんな「ピエタとトランジ」の読了とほぼタイミングを同じして観賞したのが「ゲゲゲの謎」。元々これを見ようと決めた理由は、Twitter上で自分と感性が合うと勝手に思っている映画レビュアーさんのレビューで「WW2の日本軍の特攻を無駄死にと断じていた」「美化されがちな戦後社会の発展を、資本主義的搾取と奪い合いの構造、家父長制という抑圧装置のもとに成り立った欺瞞を描いていた」というのが、日本映画(しかもアニメーション)としては割と新鮮では、って感じて見に行った、といったものでした。ついでに主役が木内秀信さんと関俊彦さんだったし。
実際、レビューで触れられていた内容は、まさにそのとおりであり、その点については創作におけるWW2や戦後社会の描き方が一歩進んだのかもしれないという意味で、大きな価値のある映画だったと思います。これまではこの辺、一般市民が受けた被害の事実や戦後復興の都合いい面ばかりが描かれてはいた感じでしたから(はだしのゲンなどの例外もありましたが、というかはだしのゲンフォロワーは結局現れなかったんでしょうか?)、次は大日本帝国や旧日本軍の加害の事実に真摯に向き合った創作が出て、あわよくばヒットしてくれればいいなと思ったものです。
その一方で、納得がいかない、というよりは、観てしばらくの間引き摺った点もありました。作中には、龍賀沙代という女性が登場します。彼女は、家の繁栄のためだけの生活を嫌い、村や家からの脱出を嘱望しており、偶然現れ、自分の家の秘密を知りたがる水木に対し、彼に協力する代わりに自分の夢をかなえる手伝いをしてほしいと、協力関係を結びます。家のために個を犠牲にする家父長制的抑圧にさらされながら、そこからの自立のために機会を練って行動するしたたかな女性である一方で、その抑圧装置における性的搾取の被害者としての一面もあり、その過程で抱え続けた傷により、最終的に彼女は破滅の運命をたどります。彼女が望んでいたのは一貫して家父長制的支配からの脱却かと思っておりましたが、多分それだけじゃなく、自分がその抑圧装置から受けた傷とそれによる怒りや憎しみといった感情を、それらを内包した自分という存在を「見て」もらうことだったんじゃないかなと思い、それらが何一つ通ることなく燃やし尽くされたという事実が、私にとって衝撃的だったのだと思います。「ピエタとトランジ」の二人も、最終的にたどったのは破滅でしたが、彼女らは何度も分断の危機に陥りながらも、それらを互いの存在により跳ねのけて、自分たちのままに破滅へ向かいました。しかし、沙代にはそんなピエタにとってのトランジ、トランジにとってのピエタみたいな存在が全くいなかった結果、自分のままに破滅したのは同じなのに無念さや理不尽を感じずにはいられなかった。
また、「ピエタとトランジ」「ゲゲゲの謎」の後に、「わたしたちが光の速さで進めないのなら(著:キム・チョヨプ)」を読んだのですが、その中の短編の一つ「巡礼者たちはなぜ帰らない」という作品で、「愛とは、現実の不条理に対して共に立ち向かうこと」だと知ったから、不条理のない箱庭の世界には戻らず、地球という不条理に満ちた巡礼先の世界に、その現地に住んでいた心を通わせた人と共にあることを選んだという一幕がありました。これがすごく自分の胸にすっと響いて、「ピエタとトランジ」に見た光の正体でもあり、「ゲゲゲの謎」の龍賀沙代が掴もうとして終ぞ掴めなかった光だったのかもしれないと、そんなことを思えました。
長くなりましたが、この3作品を連続で観賞したことが、自分にとってシスターフッド文学の門を叩くきっかけになったのです。
自戒-単なる消費・盗用にならないように
そんなわけで、シスターフッド文学を今は好んで読むようになっているわけですが、ここで常に自戒を込めて肝に銘じておかなければいけないことがあることも、私は知っています。
まず、私がシスターフッド文学を読むことを、単なる消費行為にはしたくない、いえ、してはいけない、ということです。「ピエタとトランジ」の二人の人生、美しい…だけで終わったりとか、「あいにくあんたのためじゃない(著:柚木麻子)」で、ミソジニーのおっさんたちがひと泡吹かされてスカッとした、とかそういうの「だけ」で終わること。それ自体は別に悪くないと思うのですが、少なくとも私はそれで終わっちゃいけない、ということを前置きしておきます。
私は、自分自身のアイデンティティはどこにあるのか、がいまだにあやふやです。だからその点についてはまだここでは明言を避けたいですが、それを理由に、無自覚に犯してきた罪があります。それは、今までこの記事で取り上げてきた家父長制や男性優位社会構造といった抑圧装置、排除装置に対して、その規範に対してずっと違和感を持っていたにもかかわらず、それらに対する抜本的なprotestをしてこなかったことです。その違和感をより深堀することを、何かと理由をつけてやってこなかった。それが私の罪の一つです。違和感を放置することで、私は何回もその時規範から自己を確立したがっていた自分を殺してきたのです。黙殺、という形で。そしてその違和感の先に在る、ずっと存在していた抑圧装置による秩序の中で想定されていない人たちの存在を、ずっといないものにしてきたのです。それが自分の罪。
だからこそ、シスターフッド文学における抑圧装置やその上に成り立つ秩序の存在は、絶対に外してはならないし、そこで在り続け、連帯するシスターたちの魂の声を物語を通じて知り、感じなければならない。それを現実へ還元しなければならない。罪滅ぼし、なんてことを言うつもりはありません。自分の罪を注ぐためだけに文学を使うのはそれも安直な消費と同じだと思っているので。
シスターフッド文学を数冊読んで、惹かれているのは、そうして過去殺してきた何人もの自分が導いているからかもしれない。つまり、自分にとってシスターフッド文学は、呼び覚ますための、Rebirthのための道程なのかもしれません。ずっといないものとしてきた存在達、その中には過去殺した自分もいたはず。それらを今からでも知り、感じ、そして動く。そういった、作品を通じて私を知り、世界を知り、根源的な感情から目を逸らさず、それを言語化し、発信していき、自らの行動も合わせていく。そんな、秩序装置の緩やかな合意に呑み込まれないprotestのための行動の一つとして、シスターフッド文学を捉えたいと思っています。