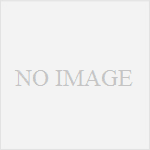今月の上旬くらいだろうか、とある読書感想を見て、興味が湧いて手に取ってみた一冊。名前自体は知っていたけど本当にそれくらいで、内容自体は全くの初見だったから新鮮な気持ちでの読書体験ができたと思う。
作品自体は、主人公であるチャーリィ・ゴードンの経過報告という手記のような形で構成されている。つまりはチャーリィの一人称視点での話ということなのだけど、後半からは単なる一人称視点、というわけでもなくなってきている。そしてわたしは自分のアイデンティティ(これも流動的なものであるけども、それでも現時点での立ち位置として)から、ジェンダークィア(aro/ace,they/them)の視点で読み進めていた。それを念頭に自分なりの感想をまとめたい。
最後のチャーリィが見た世界と決意に、ほんの一瞬だけ自分の姿が見えたような気がした。
あまりにも抽象的過ぎるけど、でもこの作品を見て感じた一番大きなことはそれだった。そしてそういう感覚は、わたしの読書体験の中では本当に瞬間的、刹那的ではあるけどそれが長く続く、持続的な、場合によっては恒久的なものなので、良い体験だったのは間違いない。
今のわたしは、人間が相互に一定以上の間重なり合うことはないと思っていて、だからこそ瞬間的にでも、一時的にでも各々の生き方が重なり合うその瞬間に輝きがあるものだと思っている。この作品は、わたしの視点から見ると、一貫してわたしのような存在は、いないもの、あるいは劣った存在として扱われているように思えて、チャーリィの知能の進歩に伴う行動の変化は、自分にとっては自分の存在を否定されているように思えて読み進めれば進めるほど苦痛を伴うものだった。
具体的には、チャーリィは知能の向上実験を受ける際に、アリス・キニアンという教師に精神的な支えを受けるのだけど、知能が向上していくにつれてそこに恋愛感情だったり性的欲求だったりが芽生えてきて、それに準じた行動にも出ようとする。そしてそれが、「男として正しい成長」みたいな扱いになっていたわけで、まあこの描写一つとってもわたしにはきついものがあった。愛情を抱いた存在に対しては、恋愛感情だったり性的欲求だったりを持つようになるのが進歩だというのならば、それを抱かない人間はなんなのか。存在しないのか、劣った存在なのかと。
そしてチャーリィの知能が発展していけばしていくほど、チャーリィは誰かを言いくるめたり説き伏せてやろう、といった言動が増えていく。今までは自分に何かを教えてくれた先生のような存在よりもはるかに多くの知識を持つようになったものの、それに比例するだけの愛情を受けていなかったチャーリィは、それを埋め合わせようとするかのように傲慢に、支配的になっていくようにわたしは見えた。
いくら知識量が増えたとしても、その知識をもって向かい合うのは自分、他者含めた地球上の存在達であり、その存在達との向き合い方を考えないと、考えられるだけの愛情を受けていないと自らが傲慢で支配的になっていき、その結果人が離れ、愛情が満たされない結果自らも深く傷ついてしまう。後半のチャーリィはまさにこの連鎖の袋小路の中にいるようだった。
そんなチャーリィだったが、実験前は見下していたネズミのアルジャーノンに対して、天才になってからは唯一心を許していたかのように向き合っていたのが印象的でもあった。アルジャーノンは同じ実験を受けていたから、あの時のチャーリィにとっては唯一自分の苦悩を分かち合える存在だったのかもしれないし、だからこそタイトルの通りのことを終盤チャーリィが欠かさず、そして最後の最後まで忘れなかったことが印象的だった。
そしてそんな自分にとっては苦しい描写が多かった中迎えた終盤、チャーリィは天才になったことで世界にずっと存在ていた様々なものを知ることができて、自分も、そして自分以外の人間のことも、ずっと存在していた人間なんだということを知ることができた。だからもう一度少しずつ勉強して、その知った時の感動をまた得たい、といった形での結びになるのだけど、ああ、多分わたしはこの場面を見るためにそれまでの描写に苦痛を感じていたんだな、と思えた。ずっと存在を否定されてきたような描写が、天才チャーリィの視点からはなされており、そのチャーリィ自身もいないもの扱いされることが多くて、それでもチャーリィは自分も、相手もずっと存在していた人間であることを知って、今度はそれを忘れずにまた学び直していこうとなった。実験でなった天才の世界には、いわゆる社会における天才である以上、いないもの扱いされる存在というものがたくさんいて、チャーリィもまたその一人で、だけどそのチャーリィにはそういう人たちもずっと存在しているということが確かにある。多分これは、ある意味ではチャーリィと同じ存在であったアルジャーノンの存在も大きかったんだと思う。アルジャーノンの死後の描写は、チャーリィの中でのアルジャーノンの存在の大きさを表していたんじゃないかなと。本当に一瞬だったけど、チャーリィの世界には見えていたんだろうなと。一瞬だけど世界が交差した、そんな感覚を得ることができた。
知能を得ることと愛情を受けること、そして世界が広がること、広がった世界を見ること、ずっと存在している存在があるということを忘れないこと。チャーリィが忘れなかったことがそれだというのがわたしにとってはあまりにも大きかった。時間だけで見たら苦しい時間の方が多かったけど、その大きい最後を見られたことが本当に良かった。でもその最後だけじゃダメで、一冊通してこの流れで得られたことが大きかったと思う。多分自分の存在に悩み、途方に暮れた時にまた読む日が来るかもしれない。多分その時は、もっとチャーリィを、チャーリィ周りの人たちを優しい視点で見られたらいいなって思う。